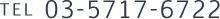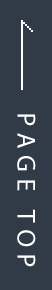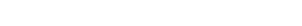【歯科麻酔の基礎知識】歯医者で使われる麻酔の種類と注意点を解説!
「歯の治療=痛い」というイメージを持っている方も多いと思いますが、現代の歯科治療では“麻酔”を使うことで、痛みをほとんど感じずに治療を受けられるようになっています。
今回は、歯科治療で使われる麻酔の種類とその効果、治療後の注意点について詳しく解説していきます!
歯科で使われる麻酔とは?
歯科治療で使用される麻酔の多くは、「局所麻酔」です。
局所麻酔とは、意識がある状態のまま、治療する部分だけに麻酔をかける方法で、歯の治療において最も一般的です。
歯科麻酔の種類【3タイプを解説】
① 表面麻酔(ひょうめんますい)
-
使うタイミング: 注射をする前
-
特徴: 麻酔針を刺すときの「チクッ」とした痛みを軽減
-
使用方法: ジェル・液体・スプレーなどを歯ぐきに塗る
-
効果時間: 約10〜20分
表面麻酔は、主に小さなお子さんや痛みに敏感な方に使われます。
② 浸潤麻酔(しんじゅんますい)
-
使うタイミング: 虫歯治療や抜歯などの一般的な処置時
-
特徴: 歯の周囲の歯ぐきに注射して、骨の中の神経に麻酔を効かせる
-
効果時間: 約2〜3時間
歯科治療で最も多く使われる麻酔です。軽度~中等度の痛みをしっかり抑えることができます。
③ 伝達麻酔(でんたつますい)
-
使うタイミング: 奥歯の治療、麻酔が効きにくい部位
-
特徴: 神経の根元に直接麻酔し、広い範囲に効果あり(舌・唇など)
-
効果時間: 約5〜6時間(個人差あり)
広範囲に効かせたいときや、麻酔の効きづらい方に用いられます。
麻酔後の注意点【必ずチェック!】
麻酔をした後は、以下のことに気をつけましょう。
❌ 血流が良くなる行動は控えて!
-
激しい運動
-
長時間の入浴
-
飲酒
血流が促進されると、痛みや腫れが出やすくなることがあります。特に抜歯などの外科処置後は要注意です。
❌ 飲食は麻酔が完全に切れてから!
-
唇・頬の感覚が鈍くなっているとうっかり噛んでしまうことがあります。
-
熱い飲み物も、火傷の原因になるのでNG!
特にお子さんは自分で感覚の違いに気づきにくいため、麻酔後はしっかり見守ってあげましょう。
麻酔が効きにくいこともある?
麻酔の効き目は、以下のような要因で個人差があります。
-
体質(麻酔が効きにくい体質の方もいます)
-
骨の厚さ
-
強い炎症がある状態
「麻酔しているのに痛い!」という場合は、絶対に我慢せずに歯科医師に伝えてください。
必要であれば、追加で麻酔を行うことで痛みを抑えることができます。
麻酔をうまく使って快適な歯科治療を!
歯科治療での麻酔は、患者さんが安心して治療を受けるための大切なステップです。
痛みに敏感な方でも、麻酔の工夫や種類を変えることでほとんど痛みなく治療を受けることができます。
わからないこと、不安なことがあれば、遠慮なくご相談ください😊
「麻酔が怖いから歯医者に行けない…」そんな方も、ぜひ一度ご来院を!