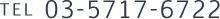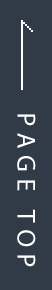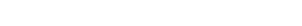【子どもと指しゃぶり】いつまでにやめるべき?影響と対処法
指しゃぶりはいつから始まる?
「子どもの指しゃぶりが心配」「いつまで続けても大丈夫?」
そんな不安を抱える親御さんは少なくありません。
実は指しゃぶりは、お母さんのお腹の中にいる「胎児期(胎生期)」から始まっているといわれています。
-
生後2〜3ヶ月頃から見られ、生後4ヶ月頃までは無意識な行動
-
5ヶ月頃には物を手に取ってしゃぶることで、形や味を学習
-
1歳以降になると、眠い時・退屈な時などに見られることが多くなります
【1歳までの指しゃぶり】心配しなくて大丈夫
生後1歳くらいまでの指しゃぶりは、本能的で生理的な行動です。以下のような意味があります:
指しゃぶりがもつ3つの役割
-
吸いつきの原始反射
→ 唇に触れたものに反応して吸う、本能的な行動です。 -
心を落ち着ける働き
→ 寂しい・眠い・退屈などの不安な気持ちを落ち着かせます。 -
口を通じた学習と確認
→ 赤ちゃんは手やおもちゃをしゃぶって形や感触を確かめています。
この段階の指しゃぶりは、無理にやめさせる必要はありません。
【指しゃぶりが長引くと…】考えられる悪影響
ただし、指しゃぶりが3歳以降も継続する場合は、注意が必要です。以下のような口腔トラブルや体への影響が起こることがあります。
指しゃぶりによる悪影響
-
☑️ 出っ歯・開咬・交叉咬合(かみ合わせの異常)
-
☑️ 歯列が狭くなる(狭窄歯列弓)
-
☑️ 上下のあごのバランスが不安定に
-
☑️ 口がいつも開いてしまう癖
-
☑️ 発音の不明瞭さ
-
☑️ 顔立ちのバランスに影響
-
☑️ 指自体にタコや変形などの影響
【年齢別】指しゃぶりとの向き合い方
▶ 3歳までの子ども
無理にやめさせず、自然に減っていくのを見守ることが大切です。
▶ 3〜6歳ごろ
友達との遊びや集団生活の中で、指しゃぶりの頻度は自然に減少します。ただし、環境の変化やストレスで逆に増えることもあるので、優しく対応しましょう。
▶ 6歳以上
指しゃぶりが残っていると、歯並びや発音に影響が出る可能性が高くなります。専門的な対応も検討する時期です。
指しゃぶりをやめるための5つのアプローチ
1️⃣ 怒らずに優しく言い聞かせる
「指しゃぶりが歯に悪いんだよ」とわかりやすく話してあげましょう。安心できる代替行動(ぬいぐるみを抱くなど)も有効です。
2️⃣ やめられたらしっかり褒める
「今日は指しゃぶりしなかったね!」と、ポジティブな声がけで自信を育てます。
3️⃣ 運動を増やす
外遊びやスポーツを通じてストレス発散と口・手の活動を促します。
4️⃣ 手遊びや工作を取り入れる
絵を描いたり紙を折ったりと、手を使う活動で指を口に持っていく行動を防止。
5️⃣ スキンシップを増やす
不安を和らげるには、親の抱っこや手つなぎが一番の安心材料です。
日常のケアも大切です
指しゃぶりをする子は、口元に指を入れる習慣があるため、衛生面の配慮も必要です。
-
一緒に手洗いをする
-
指先のケアや清潔保持
-
口内炎やタコなどの異常があれば歯科で相談
指しゃぶりに悩んだら、まずは相談を
子どもの指しゃぶりは、発達の一環として自然なものです。焦ってやめさせようとせず、お子さんの気持ちに寄り添った対応を心がけましょう。
ただし、長期化や6歳以降の継続は、歯並びや発音に影響が出る可能性があるため、気になる場合は小児歯科に早めの相談をおすすめします。
長岡歯科では、お子さまの癖や口腔内のご相談を受け付けています
お気軽にご相談くださいね♩