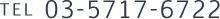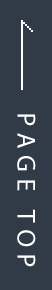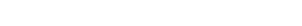歯茎の腫れ、放置していませんか?
「歯ぐき少し腫れてるけど、まあそのうち治るかな〜」
「歯医者って、痛くなったら行くものでしょ?」
こんなふうに思って、歯茎の異変をつい放置してしまう方実は少なくありません。
しかし、実はその“ちょっとした腫れ”や“出血”が、
体全体の健康に関わってくる可能性があるとしたら…
どうでしょうか、、、?

近年、歯周病が全身のさまざまな疾患と関係していることが、数多くの研究で明らかになってきました。
今回は、「歯周病と全身疾患の関係」についてまとめていこうと思います。
【見逃されやすい“沈黙の病気”】
歯周病とは、歯と歯茎の境目(歯周ポケット)に細菌がたまり、
歯ぐきや歯を支える骨に炎症を引き起こす病気です。
進行すると、歯茎が下がったり、
歯がぐらついたりし、
最終的には歯を失うこともあります。
歯周病の初期段階では、痛みなどの目立った症状が出ないことが多く、
「気づかないうちに進行していた」というケースが非常に多いのが特徴です。
日本人の成人の約8割が、何らかの歯周病にかかっているとも言われています。
ですが、それが単に「歯の問題」にとどまらないことが、知られるようになってきました。
まず、
● 糖尿病
歯周病と糖尿病は、互いに悪影響を与える“相互関係”にあります。
糖尿病によって免疫力が落ちると、歯周病が悪化しやすくなります。
逆に、歯周病の炎症によってインスリンの働きが妨げられ、血糖値が上がりやすくなることもあります。
つまり、歯周病を治療することで糖尿病の状態が改善することもあるのです。
● 心筋梗塞・脳梗塞
歯周病菌が血管内に入り込むと、血管の内側に炎症が起こります。
これがきっかけとなり、動脈硬化が進行する可能性が指摘されています。
結果として、心筋梗塞や脳梗塞などの命に関わる病気のリスクが高まることがあります。
● 誤嚥性肺炎
特に高齢者に多いのが、この誤嚥性肺炎です。
食べ物や唾液を飲み込むときに、歯周病菌を含んだ細菌が気道に入り、肺で炎症を起こすことで発症します。
高齢になると嚥下機能が低下するため、口腔内の細菌の管理は重要になります。
● 妊娠合併症(早産・低体重児)
妊娠中に歯周病があると、早産や低体重児出産のリスクが高まるとされています。
これは、歯周病による炎症性物質が子宮の収縮を促す作用を持つためと考えられています。
妊娠を予定している、または妊娠中の方には、口腔ケアをより丁寧に行うことが推奨されています。
● 骨粗しょう症
骨粗しょう症では、全身の骨密度が低下しますが、歯を支える骨(歯槽骨)も例外ではありません。
骨がもろくなることで歯周病の進行が早まり、逆に歯周病の炎症が骨吸収を促すという関係も報告されています。
特に閉経後の女性は要注意です。
なぜ歯ぐきの病気が全身に影響を与えるのでしょうか?
歯周病と全身疾患の関係には、いくつかのメカニズムが関与しています。
① 血流を通じて菌や毒素が全身へ
歯周病が進行すると、歯ぐきの内側にある血管が破れやすくなります。
そこから歯周病菌や、その死骸が出す「内毒素(エンドトキシン)」が血流に入り、全身に運ばれます。
このようにして、本来無菌であるはずの臓器や血管に、炎症が広がっていくと考えられています。
② 慢性的な炎症が体の免疫バランスを乱す
歯周病は慢性炎症です。その炎症反応によって放出される物質(サイトカインやプロスタグランジンなど)は、
免疫系・代謝系に悪影響を及ぼすことがわかっています。
たとえば、これらの物質がインスリンの働きを妨げて糖尿病を悪化させたり、
血管の壁を傷つけて動脈硬化を促進したりする可能性があります。
歯周病は、日々のセルフケアと、定期的な歯科受診によって、予防も改善も可能な病気です。
お口の健康を守ることは、結果的に体全体の健康につながります。
✴︎予防のポイント✴︎
- 毎日の正しいな歯みがき
- 歯間ブラシやフロスを使った歯間清掃
- 3〜6ヶ月に1回の歯科検診とプロのクリーニング
- 喫煙習慣の見直し(歯周病の大きなリスク因子です)
- 全身疾患がある方は、主治医と歯科の連携
これまで「歯ぐきの出血や腫れはたいしたことない」と思っていた方も、
実はその小さなサインが、体のさまざまなトラブルの入り口になっているかもしれません。
歯周病は、気づきにくく、でも確実に進行し、
そして、全身の病気に静かに関わっていく病気です。
「健康に気をつけたい」「病気を予防したい」
そう思う方こそ、ぜひお口の中にも目を向けてみてください。
歯ぐきを健康に保つことは、
将来的な糖尿病の予防・心疾患のリスク低減・妊娠合併症の回避など、体全体を守ることにつながります!
なにか気になる点ございましたらお気軽にご相談してください。