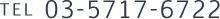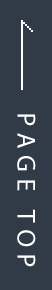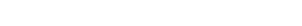腸活と歯科の深い“つながり”とは?〜口腔環境と腸内環境の相互関係〜
最近よく耳にする「腸活(ちょうかつ)」。実はこの腸活と歯科・口腔環境には密接なつながりがあることをご存知でしょうか?
「口腸相関」――口と腸はつながっている!
歯科の世界でも注目されているのが「口腸相関(こうちょうそうかん)」という考え方。
これは、口腔内フローラ(細菌叢)と腸内フローラが密接に関連しているという理論です。
-
口内環境が悪化すると、虫歯菌や歯周病菌が増殖
-
その菌が唾液とともに体内に入り、腸内環境を乱す可能性
-
反対に、腸内環境の悪化も口腔内の菌バランスを崩す要因に
つまり、腸と口は一方通行ではなく“相互に影響”し合っているのです。消化管でつながる両者は、まさに健康の土台を担うパートナーです。
歯周病菌が腸内に?知らないうちに体内へ…
私たちは1日に約1〜1.5ℓの唾液を飲み込んでいるといわれています。
もし、起床後すぐに歯を磨かず水を飲むと、口の中に潜む細菌を直接飲み込んでいることに…。
さらに、歯周病や虫歯がある人は、病原菌を日常的に腸へ送り込んでいるリスクが高まります。
胃酸で死ななかった菌が小腸・大腸まで届くため、口腔内細菌のコントロールが腸活のカギとなるのです。
大腸がんとの関連も?
近年の研究では、「ソフバクテリウム・ヌクレアタム(Fusobacterium nucleatum)」という歯周病菌が、大腸がんの発がん・進行と関係していることも報告されています。
口腔内のケアが、将来の疾患予防にまでつながっているのです。
腸活のために「よく噛むこと」も重要!
腸活の基本として「よく噛むこと」が挙げられますが、これも歯科の観点から非常に大切な要素です。
よく噛むメリット:
-
唾液の分泌を促進(アミラーゼなどの酵素で消化を助ける)
-
腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)を促進し、便秘改善に
-
善玉菌のエサを作る(よく噛むことで食物繊維が細かく砕かれ、腸内環境を整える)
-
脳の活性化や満腹中枢の刺激により、食べすぎ防止にも貢献
つまり、「噛む力を維持することは、腸活にも直結している」ということ。
そのためには、虫歯や歯周病の予防・治療は欠かせません。
腸活を始めるなら、まずお口の見直しから!
腸活といえば発酵食品やサプリに注目しがちですが、“口腔ケアも立派な腸活”です。
-
毎日の正しい歯みがき習慣(セルフケア)
-
歯科医院での定期的なメンテナンス(プロケア)
-
歯周病や虫歯を放置しない
これらを意識することで、腸内環境も整い、全身の健康に繋がっていくのです。
腸活と歯科の「つながり」を見直しましょう。
腸と口は、体の入り口と出口を結ぶ“健康のバイパス”。
歯科的な視点から腸活を見直すことで、より根本的な健康づくりが可能になります。
ぜひ今日から、「腸活=口腔ケア」という視点を取り入れてみてください。